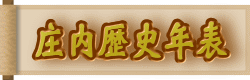
| 私たちは、庄内に生まれ育ち、百年にも満たない平凡な人生を終わります。 幾千年も続いたであろう人類の歴史を考えるとほんの一点にも当たらない存在であるに違いありません。しかし、この郷土『庄内』が、どのような流れを過ぎ、将来どのように発展していくかを記録として残す必要があると考えます。 |
| 縄文時代 | 紀元前(2500) | 深萩黄金遺跡 |
| 弥生時代 | 紀元前(300) | 協和の白河原遺跡 |
| 大和時代 | (300) | 亀塚 舘山寺 御山塚 |
| (500) | 根本山古墳群 火穴古墳 | |
| 飛鳥時代 | (612) | 湖北浜名橋の架橋 |
| 大宝1年(701) | 乙君の五保の制 | |
| 奈良時代 | 神亀4年(727) | 愛宕神社の創建 |
| 天平勝宝1年(749) | 乙君の長福寺(医王寺)創建 | |
| 神護景雲1年(767) | 曽許乃御立神社創建 | |
| 不明 | 八幡神社創建 | |
| 不明 | 呉松の津島神社創建 | |
| 平安時代 | 弘仁1年(810) | 舘山寺創建 |
| 承知1年(834) | 内山村の津島神社創建 | |
| 寛平1年(889) | 和田村の西宮神社(旧)創建 | |
| 延長5年(927) | 曽許乃御立神社が延喜神名式に選ばれる | |
| 鎌倉時代 | 正暦4年(993) | 藤原共資が巡倹使として村櫛の志津城に住む |
| 寛弘7年(1010) | 共資の子共保が生まれる(井伊氏の祖) | |
| 承安3年(1173) | 村櫛荘が最勝光院領となる | |
| 寿永2年(1183) | 湖北浜名橋を湖南橋本に移す | |
| 承久3年(1221) | 共資の子孫に当る日蓮が生まれる | |
| 建長5年(1253) | 日蓮が法華宗を開く | |
| 文永年間 (1264)〜(1274) |
日蓮の須之木沢村伝説 | |
| 正中1年(1324) | 村櫛荘が京都の東寺領となる | |
| 南北朝 時代 |
貞治年間 (1362)〜(1367) |
藤原基秀が堀江城に住むその子基久のとき大沢を姓とする |
| 応安1年(1368) | 半済法廃止により年貢が東寺に届かないと訴える | |
| 嘉慶2年(1338) | 村櫛荘で年貢の替銭として割符を送る | |
| 室町時代 | 応永年間 (1394)〜(1429) |
堀江光真が佐田城主となる |
| 内山の如意寺大いに栄える | ||
| 大般若経六〇〇巻の写本 | ||
| 応永3年(1396) | 大地震が起こり被害大 | |
| 応永12年(1405) | 津波による被害 | |
| 元中〜文亀 (1390)〜(1503) |
村櫛九郎の活躍 | |
| 永享11年(1439) | 今川氏の臣井伊弥四郎が志津城を攻める | |
| 寛正3年(1462) | 堀江久実の母妙智院が三ヶ日町大崎に法憧院を創建 | |
| 文政1年(1466) | 宿芦寺創建 | |
| 文明5年(1473) | 量光庵が深萩の水出に創建される | |
| 文亀1年(1501) | 堀江為清が三ヶ日町金剛寺に寺領を寄付 | |
| 戦国時代 | 文亀3年(1503) | 村櫛九郎 堀江為清らは斯波義寛に協力して社山城主二俣氏と戦う |
| 永正1年(1504) | 大沢基房 堀江為清が今川氏に降りる | |
| 村櫛荘が解体して大沢領となる | ||
| 永正2年(1505) | 大沢基房が北条早雲に従って岡崎城主松下長親を攻める | |
| 永正6年(1509) | 大沢基房が共に二俣城を助ける | |
| 永正7年(1510) | 村櫛の宝谷寺が大津波のため湊崎より漂着 | |
| 永正9年(1512) | 大河内貞綱が斯波氏が志津城を攻めたが失敗 | |
| 大永2年(1522) | 佐田城が落ちる桜塚と稚子岩の伝説 | |
| 天文2年(1533) | 大沢基相が村櫛に住む今川氏輝より浜名湖往来の船舶を司ることを命ぜられる | |
| (1554) | 呉松の曹洞院がつぶれる | |
| 天文5年(1536) | 四柱神社の棟札 | |
| 天文8年(1539) | 佐田村の百姓ら堀江氏の仁徳を慕って村名を堀江村と改めた | |
| 天文12年(1543) | 内山村の東福寺創建 | |
| 天文13年(1544) | 大沢基相が堀江城に帰り、今川義元より上田村の検地の増分を与えられる | |
| 天文18年(1549) | 紅林甚二郎が今川義元より三河国上野端城攻めの感状を与えられる | |
| 弘治3年(1557) | 中安兵部が堀江城主であったと言われる | |
| 永録3年(1560) | 中安兵部が竜泉寺を大草山頂に創建 | |
| 永録4年(1561) | 大草山の満願寺が大いに栄える | |
| 永録5年(1562) | 検地増分について中安兵部が訴えられる | |
| 永録6年(1563) | 大沢基胤は井伊氏の臣中野氏らと曳馬城を攻めて戦功をあげる | |
| 永録11年(1568) | 遠藤景誠が家康の遠江入りの道案内をする | |
| 永録12年(1569) | 家康が大沢基胤の属城堀川城を攻め落とす 家康は井伊谷三人衆に命じて堀江城を攻めさせる 堀江城善戦したが降伏する 志津城兵が堀江城を助ける | |
| 元亀1年(1570) | 中安兵部が姉川の合戦に家康の馬前で討死 家康は曳馬城を浜松城と名つけて入城 | |
| 元亀1年頃 (1570)頃 |
大津波によって漂着した人たちが新居の角避彦神社を八王子大明神と共に祀る | |
| 元亀3年(1572) | 野中三五郎が三方原合戦に家康から褒称の盃を与えられる | |
| 遠藤景誠が三方原合戦に奪戦して討死 | ||
| 志津城が武田軍に攻められて多くの死傷者を出す | ||
| 堀江城が武田軍に攻められたが武田軍は囲みを解いて引き上げる | ||
| 天正1年(1573) | 遠州大念仏の起源 | |
| 天正3年(1575) | 大沢基胤が長篠の戦いに参加 | |
| 天正5年(1577) | 竜泉寺を大草山頂から現在地(内山)へ移す | |
| 天正年間 (1573)〜(1591) |
村櫛村平太夫が島浦の運上金を免許される | |
| 安土桃山時代 | 天正7年(1579) | 野中三五郎が築山殿を殺害する |
| 天正8年(1580) | 大沢基宿が田中城(藤枝城)攻めに参加その臣新村新七郎が戦功により感状と槍を与えられる | |
| 天正10年(1582) | 大沢基宿が本多重次と共に沼津城(三枚橋城)を攻める | |
| 天正12年(1584) | 小牧山の合戦で大沢基宿は家康の命により中安康勝と共に清州城の二の丸を守る | |
| 天正16年(1588) | 大沢基宿は聚楽第において特に従五位下侍従に叙せられる | |
| 天正18年(1590) | 大沢基宿は小田原合戦の折武州岩槻城を攻めるこのとき中安康勝は上州安中で自害 | |
| 天正18年(1590) | 堀江城の権太織部は家康に従って江戸に行く | |
| 慶長年間 (1596)〜(1614) |
内山村の東福寺がつぶれる | |
| 江戸時代 | 慶長5年(1600) | 関ヶ原合戦に大沢基宿は本多忠勝の軍に属して戦功をたて敷智郡のうち1550石の加増 |
| 慶長6年(1601) | 八柱神社が黒印二石の寄進をうける | |
| 慶長10年(1605) | 大沢基胤が八十才で死亡 | |
| 慶長14年(1609) | 大沢基宿が従四位下近衛権中将に任ぜられ高家に列せられる | |
| 元和1年(1615) | 大沢基宿父子が大阪夏の陣に参加 | |
| 元和2年(1616) | 大沢基宿が家康の葬儀に参列 | |
| 不明 | 大沢基宿の弟基雄が分家独立 | |
| 元和5年(1619) | 庄内地方を大早魃大洪水が襲う | |
| 元和6年(1620) | 大沢基宿が幕府の謝恩史として上洛 | |
| 元和七(1621) | 大沢基宿は七十六才で病没し宿芦寺に葬られる | |
| 大沢基浩(分家)が台徳院に仕える | ||
| 寛永年間 (1624)〜(1643) |
五人組の制度が確立 | |
| 寛永2年(1625) | 大沢基重はえど宅地制度により江戸屋敷を造る | |
| 寛永16年(1639) | 大沢基将が従四位下大輔奥高家に抜擢される | |
| 正保1年(1644) | 平松村の泉竜寺がつぶれる | |
| 承応1年(1652) | 上田村の松林寺が大火焼失 | |
| 承応2年(1653) | 平松寺跡へ八幡神社を還宮 | |
| 承応年間 (1652)〜(1654) |
量光庵がつぶれる | |
| 明暦1年(1655) | 堀江村の常在寺へ賊が入って本尊をこわす | |
| 万治1年(1658) | 如意寺がつぶれる | |
| 寛文3年(1663) | 呉松村の宝珠寺創建 | |
| 寛文4年(1664) | 村櫛村の宝泉寺創建 | |
| 村櫛の採藻訴訟事件 | ||
| 寛文8年(1668) | 和田村の一徳寺が極貧となる | |
| 寛文10年(1670) | 村櫛村の清伝寺創建 | |
| 呉松村の長楽寺創建 | ||
| 寛文12年(1672) | 村櫛村の南江寺創建 | |
| 延宝4年(1676) | 野中友重が水戸公に仕える | |
| 延宝5年(1677) | 慈雲寺創建 | |
| 延宝6年(1678) | 和田村の清竜寺移転 | |
| 延宝8年(1680) | 内山村の真福寺が大風大潮のため大破 | |
| 貞享1年(1684) | 村櫛村の宝谷寺が大沢氏より毎年仏米二俵を受ける | |
| 貞享2年(1685) | 村櫛村の宗円寺がつぶれる | |
| 元禄年間 (1688)〜(1703) |
山神社の枯損木を売る | |
| 元禄10年(1697) | 水出観音に観音像を安置 | |
| 元禄15年(1702) | 白須村より「気賀村の誓書」を出す | |
| 元禄16年(1703) | 宇気比神社焼失 同年再建 | |
| 宝永年間 (1704)〜(1710) |
庄内で温州みかんの栽培が始まる | |
| 宝永2年(1705) | 大沢基隆が新領1000石を加増される | |
| 宝永6年(1709) | 村櫛村の海巌寺創建 | |
| 正徳2年(1712) | 内山村の真福寺大火付近の民家二十八戸全焼 | |
| 享保2年(1717) | 島浦の年貢例 | |
| 元文1年(1736) | 大沢基朝が奥高家見習いとなり従五位侍従に叙位 | |
| 延喜3年(1746) | 大沢基朝の年貢米抵当の借金証文 | |
| 延喜4年(1747) | 村櫛の大火102戸全焼 | |
| 藻草の盗採(他売)で八人が処罰 | ||
| 宝暦年間 (1751)〜(1763) |
堀江村の其流呉松村の梅路という俳人現れる | |
| 宝暦12年(1762) | 堀江村漁民が禁猟区内浦でぼらの幼魚を採って詫び状 | |
| 明和1年(1764) | 石塚竜磨が細田村に生まれる | |
| 明和年間 (1764)〜(1771) |
田畑の開墾が多くなる堀江村など十一ヶ村の開墾 大沢定寧が「南北庄内村櫛荘」の石高明細帳を公儀勘定所へ出す |
|
| 明和8年(1771) | 白須村より松平伊豆守に手形を出す | |
| 庄内地方大早害 | ||
| 安永1年(1772) | 庄内地方大洪水 | |
| 天明6年(1786) | 石塚竜磨が内山真竜の門人となる | |
| 天明8年(1788) | 大江寺全焼のため沿革不明この年碑座名簿を幕府に出す | |
| 寛政1年(1789) | 石塚竜磨が真竜に同行して「遠江風土記伝」の調査を手伝う | |
| 石塚竜磨が本居宣長の門人となる | ||
| 寛政2年(1790) | 大洪水のため村櫛堤の大畑へ小船流入藻草50駄流失 | |
| 大沢基之が奥高家見習いとなり従五位侍従に叙位 | ||
| 寛政8年(1796) | 細田村の石塚司馬右衛門や白須村の松尾源松が豊橋の斎藤一堀の門人となって算学を学ぶ | |
| 文化2年(1805) | 石塚竜磨の兄の妻の追善句会が開かれ近郷の俳人が集まる | |
| 伊能忠敬が浜名湖周辺を測量三月十九日より佐浜 白須 村櫛 堀江など | ||
| 文化12年(1815) | 大沢基之が日光奉行となり家康200回忌の法事を行う | |
| 文政3年(1820) | 大沢基昭が表高家となり従五位侍従に叙位 | |
| 文化文政年間 (1804)〜(1829) |
鹿島神社境内に寺小屋が開設されて明治五年まで続く 石塚竜磨は近郷各地の歌会に数十回出席して指導する |
|
| 文政6年(1823) | 平松村が新たに一町八反畑九町七反を開墾 | |
| 文政8年(1825)〜 天保8年(1837) |
天神町大雄庵の住僧楚州が「舘山寺吟草」二編を刊行した | |
| 天保年間 (1830)〜(1843) |
白須村の俳人時習が「春興」を発行して活躍する | |
| 天保3年(1832) | 全国的大飢饉 庄内も惨害 | |
| 赤尾憩呉松村に生まれる | ||
| 天保9年(1838) | 大沢基暢が表高家となる | |
| 安間氏と遠藤氏の本家争いが続き安間氏が本家と決まる | ||
| 天保12年(1841) | 石塚治平が細田村に生まれる | |
| 天保13年(1842) | 満願寺より浜松の法林寺へ寺請証文を送る | |
| 嘉永1年(1848) | 長雨・日照り続きで大沢氏がかゆ施工 | |
| 袴田巽が村櫛村に生まれる | ||
| 嘉永年間 (1848)〜(1853) |
浜名湖湖畔新四国八十八ヶ所参りが流行し、嘉永三年堀江村の新村松助らが参詣に旅立つ | |
| 嘉永3年(1850) | 呉松村より松平伊豆守へ手形を差し出す | |
| 嘉永6年(1853) | 呉松村の吉蔵の妻が天神山で殺害される | |
| 西村の福聚寺の宗門人改御帳 | ||
| 安政1年(1854) | 堀江村の商人善吉が神田原で殺害されて金子五両奪われる | |
| 大地震津波ひどく薩摩藩の駄荷が新居より村櫛 和田 内山に漂着 | ||
| 安政2年(1855) | 江戸に大地震が起こり大沢氏の江戸屋敷が破壊 | |
| 気賀下村の佐吉が村櫛島浦で密猟して詫び状を出す | ||
| 堀江村は高潮のため堤防が崩れ浸水家屋が多く田畑は大凶作 | ||
| 万延1年(1860) | 村櫛村で酒の専売制始まる | |
| 大沢基寿が高家となり従五位侍従に叙位 | ||
| 文久2年(1862) | 基寿は和宮降嫁のお供役となる | |
| 文久3年(1863) | 将軍上洛につき基寿はお供役となり金1000両を献金 | |
| 将軍が今切渡船につき庄内の村々より船90艘を出す | ||
| 基寿が江戸から帰国 | ||
| 慶応1年(1865) | 長州再征伐のため今切渡船につき船100艘を出す | |
| 慶応2年(1866) | 宮本玄吾が呉松村に生まれる | |
| 慶応3年(1867) | 大沢基寿が将軍の建白書を朝廷に伝奏して大政奉還となる | |
| 江戸末期 | 堀江村で新堀を堀削し開通する | |
| 明治時代 |
明治1年(1868) | 庄内地方は新居宿の助郷役を勤める |
| 村櫛村の宮下新開、内山村の宿芦寺下開田が行なわられる | ||
| 江戸混乱のため堀江藩が国元へ引き上げる | ||
| 大雨が降り続き流失家庭に蔵麦を施す | ||
| 堀江藩が勤王証書を出す | ||
| 明治天皇御東幸のため基寿は天竜川へ船橋を架ける 御還幸のときも同様 | ||
| 明治2年(1869) | 家老安間又左衛門の我意を村民が訴える | |
| 家老安間氏が持明院御判物を受ける | ||
| 暴風のため作物は全滅 基寿は極貧者に救い米を出す | ||
| 明治3年(1870) | 堀江藩でも神葬祭を認める | |
| 庄内で廃寺が続出 | ||
| 明治4年(1871) | 廃藩置県により基寿は堀江県知事となる | |
| 万石事件が起き基寿以下追放となる | ||
| 堀江県は浜松県に合併 | ||
| 明治6年(1873) | 内山学校開設 | |
| 明治7年(1874) | 呉松村に佐平往還の道路開発公社設立 | |
| 鹿島学校開校 | ||
| 堀江郵便局開局 | ||
| 明治13年(1880) | 堀江藩邸が入札競売される | |
| 明治14年(1881) | 海藻他売差止請求起訴事件発生 | |
| 明治16年(1883) | 海藻他売差止請求起訴事件は大審院にて村櫛村勝訴となる | |
| 明治17年(1884) | 石塚治平が「協和村地誌」を著わす | |
| 明治22年(1889) | 市制町村制施行により庄内九ヶ村は村櫛村 南庄内村 北庄内村となる | |
| 組合立庄内高等小学校と改称される | ||
| 村櫛村 南庄内村 北庄内村尋常小学校となる | ||
| 明治27年(1894) | 日清戦争が始まる | |
| 明治38年(1905) | 組合立庄内高等小学校新築移転(寒ノ神) | |
| 明治40年(1907) | 浜名湖巡航船就航 | |
| 明治43年(1910) | 組合立庄内高等小学校廃校 | |
| 大正時代 |
大正2年(1913)頃 | 乗合馬車開通 |
| 自転車に乗る人が現れる | ||
| 大正3年(1914) | 北庄内村立北庄内尋常小学校と改称 | |
| 村櫛村立村櫛尋常小学校と改称 | ||
| 大正4年(1915) | 庄内地方に始めて電灯がつく | |
| 大正5年(1916) | 和田の汽船営業開始 | |
| 村櫛郵便局発足 | ||
| 大正7年(1918) | 南庄内村立南庄内尋常小学校と改称 | |
| 大正10年(1921) | 県道開通 堀江まで | |
| 大正11年(1922) | 県道開通 内山まで | |
| 大正13年(1924) | 県道開通 和田まで | |
| 庄内白菜栽培始まる | ||
| 大正15年(1926) | 県道開通 村櫛北明まで | |
| 加藤米太郎南庄内小学校長 篠原の自宅からオートバイで通勤 | ||
| 昭和時代 | 昭和2年(1927) | 電話交換業務始まる(堀江郵便局) |
| 庄内にはじめて販売用の菊が作られる | ||
| 昭和4年(1929) | 随縁寺新築 | |
| 村櫛汽船営業開始 | ||
| 昭和4年頃(1929)頃 | 庄内地区にもラジオ受信機が入る | |
| 昭和5年(1930) | 舘山寺本通り開通 | |
| 電話交換業務始まる(村櫛郵便局) | ||
| 昭和7年(1932) | 乗合バスが営業開始(堀江) | |
| 昭和12年(1937) | 日支事変始まる | |
| 昭和16年(1941) | 太平洋戦争開戦 | |
| 昭和20年(1945) | 太平洋戦争終結 | |
| 昭和22年(1947) | 国民学校から北庄内小学校 南庄内小学校 村櫛小学校と改称 | |
| 村櫛村立幼稚園創立 | ||
| 村櫛公民館発足 | ||
| 昭和23年(1948) | 南庄内中学校落成式 | |
| 若葉幼稚園開園(白洲) | ||
| 村櫛村120町歩の大干拓事業完成 | ||
| 昭和25年(1950) | 北庄内中学校落成式 | |
| 宿芦寺幼稚園開園(内山) | ||
| 本田 ヤマハのポンポンが普及し始める | ||
| 昭和30年(1955) | 北庄内村 南庄内村 村櫛村 三村が合併し庄内村となる | |
| 各小・中学校が庄内村立となる | ||
| 庄内村立南庄内幼稚園創立 | ||
| 昭和30年(1955)頃 | テレビを持つ家庭が次第に増える | |
| 昭和33年(1958) | 庄内村立白州・鹿島幼稚園創立 | |
| 昭和37年(1962) | 浜名郡庄内村立庄内中学校誕生 | |
| 昭和40年(1965) | 庄内村浜松市に合併 | |
| 各幼・小・中学校が浜松市立となる | ||
| 昭和44年(1969) | 東名高速道路全線開通 | |
| 昭和45年(1970) | フラワーパーク開園 | |
| 昭和48年(1973) | 弁天島と庄内半島を結ぶ浜名湖大橋が開通 | |
| 昭和49年(1974) | 東名高速道路の浜松西インター開通 | |
| 昭和52年(1977) | 舘山寺第二温泉源湧出 | |
| 昭和53年(1978) | 三方原用水大規模圃場整備事業と畑地かんがい事業完成 | |
| 昭和55年(1980) | 舘山寺保育園設立 | |
| 昭和57年(1982) | 浜松市北庄内幼稚園誕生 | |
| 昭和58年(1983) | 浜松市動物園が開園 | |
| 平成 | 平成1年(1989) | 村櫛町に国際頭脳センターが開設 |
| 都田ダムより水をひいて根本山の中腹に浜松市水道部配水場完成 | ||
| 舘山寺第三温泉源湧出 | ||
| 平成2年(1990) | 浜松市庄内公民館落成 | |
| 平成11年3月(1999) | 庄内商工会 インターネットホームページ開設 |